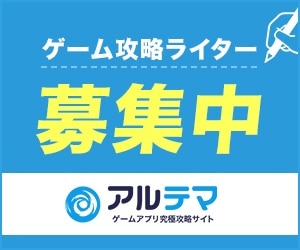Clair Obscur Expedition 33 クリアレビュー
アルテマ攻略班

- 新作アプリを見逃すな!
- ・新作アプリ配信カレンダー
Clair Obscur Expedition 33 (以下Expedition 33)は、海外産のタイトルでありながら、ファイナルファンタジーシリーズやペルソナの影響を強く受けたJRPG的な作りが話題となっているRPGだ。多くのメディアが高評価していることから、早くもGOTY候補として挙げる声も少なくない話題作である。
当記事では、そんなExpedition 33のクリア後レビューを忖度なしの正直ベースでお届けしていく。
なお、直接的なネタバレは避けているが、シナリオの傾向について終盤を含めてある程度の具体性を持って記述しているため、注意して頂きたい。
アルテマ攻略班の評価
| 総合評価 | ||
|---|---|---|
| 8.0 / 10 点 | ||
| ストーリー | バトル | グラフィック |
| ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 操作性 | 音楽 | UI |
| ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
クリアまでの時間はそれなりに寄り道をして30時間ほど。
Expedition 33はこんな人におすすめ
-
- ・PS3時代のJRPGが好き
- ・物悲しい雰囲気の世界観が好き
- ・パリィでの爽快感を味わいたい
本作は、日本産のゲームで馴染みのあるシステムを多く採用した「欧州産のJRPG」といユニークな位置づけのタイトルだ。
RPGだけでなくSEKIROに似た手触りの死に覚えゲーの要素も盛り込まれていて、コマンドバトルでありながらプレイヤースキル介入の比重が大きく、達成感を得られるバトルシステムが本作最大の魅力となっている。
一方で、システムの不足によってゲーム体験が損なわれている部分も見受けられ、とりわけ探索におけるストレスは常にプレイヤーに付き纏っていた。
また、序盤~中盤までのシナリオはミステリアスで興味を引かれるものであったが、終盤においてかつて日本のサブカルチャーのいくつかが経験した失敗と同じ轍を踏んでしまっており、物語全体を色褪せさせてしまっていたのは非常に残念である。
緊迫感と達成感のあるバトルシステム
プレイヤー側の行動のQTEは易しめ
本作のバトルシステムは、各行動にコストが伴うターン制をベースにしており、そこにQTE的な4種類の回避要素を加えたものとなっている。思い起こされるのは、FF10、ペルソナ、そしてマリオRPGだ。
パリィの判定はRPGに搭載されているものとしてはやや厳し目で、ダークソウルほどではないがSEKIROくらいにはアクション寄りの難度。
そのぶん雑魚戦含めてバトルに緊張感があり、パリィを全て成功させた時は大ダメージのカウンターと共にプレイヤーは大きな達成感を得られる。
シンボルエンカウント方式でバトルが始まるため、戦闘回数が増え過ぎるといったこともなく、クリアまで戦闘の楽しさを維持できていた点は称賛したい。
爽快感のあるパリィ
その気になれば全ての攻撃をノーダメージで処理できる大胆なシステム
プレイヤーは敵のモーションから回避&パリィのタイミングを身体で覚え、反撃の糸口を見つけていくというのが、本作のバトルにおけるセオリー。
とりわけ敵の攻撃を全てパリィした後のカウンターの威力が凄まじく、序盤から使えるパッシブに「パリィするたびに行動リソースが+1」という効果があるため、パリィのリターンが非常に大きなものとなっている。
そのぶん、パリィの難易度はやや高めに設定されているが、何度か失敗を繰り返すことでいずれはほぼ確実に成功できるようになるくらいのバランスなので、積極的に狙いたくなる塩梅だ。
カウンター演出も気持ちが良く、キャラクターとカメラの両方がアクロバティックに動いて大ダメージを出す様は、まさにJRPGっぽさを感じられた。
中盤以降は敵のモーションにフェイントやディレイが増え、攻撃回数も3段、4段、5段とどんどん増えるのでパリィを合わせるのに苦労する場面も多くなる。それによってストレスを感じることも多々あったが、それも含めて極上の達成感を得るためのスパイスになっている。
終盤ではほとんどSEKIROのような死に覚えの様相を呈してくるため、これからプレイするのであればある程度はそういった歯応えを覚悟しておいた方がいいかもしれない。
リトライ機能の不足
本作が回避とパリィを主体とした戦闘バランスであることから、強敵との戦いは「死に覚え」になりやすい。
が、戦闘そのものをリトライする機能は用意されておらず、セーブデータのロードでやり直すしかない。また、驚くべきことに本作は自動セーブのみで、手動セーブが実装されていない。そのため、ワールドマップ上にいる強敵との戦闘をやり直した際に、敵からはるか離れた場所でのやり直しになる場合が多く、バトルバランスに対するリトライ性の悪さには不満が残った。
一応、装備の付け替えだけでも自動セーブが発生するので擬似的な手動セーブは可能だが、こういった仕様を利用するのではなく手動セーブという仕様自体を用意しておいて欲しかった。
「ぶっ壊れ」を作れるビルドシステム
本作は物語の進行によって加わる最大5人のプレイアブルキャラクターの中から、3人を選んでパーティを組む伝統的な編成システムを採用している。
各キャラには固有の武器種、スキルが用意されており、冒険の中で武器を集め、強化し、スキルツリー形式でスキルを習得することでキャラクターが強化されていく。
スキルの多くは互いに補完関係にあるものが多く、例えばスキル1で火傷を付与し、スキル2のもつ「火傷の敵にダメージアップ」の効果を発生させるといった立ち回りが求められる。
条件付きの火力アップ効果がいずれも倍率が非常に高く、パーティ単位でビルドを構築することでゲームバランスを壊すほどの火力も発揮できるようになっている。
そのため、コマンドにおいて特定のルーチンを擦り続けることになるという面もあるが、古のJRPGプレイヤーであればそういった「ぶっ壊れ」に懐かしさを感じられるだろう。
ペルソナ風味のUI


本作のバトルにおけるUIは、ペルソナシリーズのようなスタイリッシュさを持ちつつ、感覚的にも使いやすい優れたものであった。
スキルを頻繁に呼び出す事になるバトルシステムでありながら、スティックや十字キーを用いた選択をする必要はなく、ボタンでポンポンと進むため軽快なコマンドバトルを楽しむのにUIが大きな役割を果たしてくれていた。
ただし、メニュー画面のUIには難があり、どこを選択しているのか非常にわかりにくく、頻繁に付け替えするパッシブスキルの選択UIの操作性にも改善の余地が多々ありそうだった。
懐かしいシステムのフィールド

本作には、JRPGファンが失って久しい「ワールドマップ」が存在する。
ワールドマップを直接歩いてダンジョンの入口を探し、ロードを介してダンジョンに挑んでいくという昔ながらのシステムは今なお魅力的で、物語進行中でもしっかり寄り道先が用意されており、昔のJRPG然としたワールドマップ探索を楽しめる作りだ。
ミニマップ無しでの探索はストレスが大きい
本作はフィールドの探索において、武器、パッシブスキル、キャラ育成に必要なアイテムが高頻度で手に入るため、なるべく隅から隅まで探索する事が推奨される設計になっている。
ところが、本作ではフィールド上でのミニマップが存在せず、メニューを開いて表示できるような全体マップも用意されていない。それどころか、方角すら一時的にしか表示されないという徹底ぶりである。
そのため、完全に「そら」の状態でフィールドを探索することになり、これがゲーム全体の体験を大きく損ねてしまっていた。とりわけ序盤はプレイ時間の大半を「迷う」事に費やされがちだった。
フィールド構造自体も俯瞰しにくくかつ記憶に定着しにくい作りなので、何かクリエイター的なこだわりがあったにせよ、ミニマップは実装するべきだったように思う。
美しく物悲しいBGM
本作のBGMは全体的にピアノ+ボーカルのマイナー調の楽曲が多く、ゲーム全体に悲壮感を漂わせるのに一役買っていた。
率直に言えば「ニーアシリーズまんま」な雰囲気である。
ニーア楽曲ほどのクオリティではなかったものの、曲1つ1つが美しく、十分魅力的ではあった。ただ、どこに行っても何をしてても似たような曲調のBGMが続くため、音楽演出としては「一貫している」というよりは「単調」という印象を受けてしまった。
洋画的なキャラクター

多くの部分でJRPG的な要素を持つ本作だが、キャラクターに関してはビジュアルと性格の両面で良くも悪くも「洋ゲー」あるいは「洋画的」だった。
表情、仕草、台詞回しにJRPG的な要素は無く、年齢設定や各キャラのバックボーンは、欧米の作品で見掛ける海外的な情緒で構成されていた。
RDR2、ゴーストオブツシマといった海外産のゲームと比較しても本作のキャラクター達は薄味なので、JRPG的なキャラクターは本作に求めないほうがいいだろう。
終盤のシナリオに難あり
本作はシナリオも大きな売りの1つであるが、終盤で明かされる物語の根幹に関わる部分は賛否がわかれそうなものであった。
もちろん賛の感想を持った人を理解できるし否定もしないが、残念ながら筆者は否の側に大きく傾いてしまった。
日本漫画のような設定から始まる物語
ペイントレスと呼ばれる謎の存在によって人間の寿命が大幅に短縮されており、33歳になった時点でその人間は強制的に「抹消」されるというのが本作の世界設定。
この寿命は1年ずつ短縮されており、人類はペイントレスを倒すべく定期的に遠征隊を送り込んでいるが、成果を挙げられていない。本作のタイトルでもあるExpedition33は「第33遠征隊」を意味するものであり、「33歳で死ぬ年度に派遣された遠征隊」という意味でつけられているナンバリングでもある。
この遠征隊はざっくり言えば進撃の巨人における調査兵団のようなものであり、残りの寿命が少なくなった人間が最期の足掻きとして遠征隊に加わって死地に赴くといった側面が強い。
主人公ギュスターヴ達もそんな第33遠征隊のメンバーであり、33歳の抹消が起きていよいよ来年は自分の番になった人物達がペイントレス討伐に向かう……というのが本作のプロローグとなる。
キャラクター自体は海外然としているものの、導入は日本のゲーム・漫画・アニメのファンであれば入りやすいものだと言えるだろう。
続きが気になる展開の連続
直接的なネタバレは避けるが、本作のシナリオは比較的短い間隔で物語に直接関わる大きな展開を見せてくれる。
序盤から早々に興味を引く展開が続き、「続きが気になる」という物語を追う上で最も重要な欲求を常に喚起させてくれる、謎が謎を呼ぶタイプのストーリーだ。
実のところ、最終盤までは「結局この世界の根幹は何もわからない」に等しい状態が続いてしまうものの、演出が上手いのでシナリオに引き込む力は非常に強い。
そのため、序盤~中盤の物語体験は良好で、中盤までであれば「シナリオゲー」として高い評価ができる。
終盤の展開は……
中盤までは、悲壮な決意で絶望的な世界に抗う主人公達の姿が描かれ、壮大な世界観と多くの謎がプレイヤーを物語に引き込んでくれる。が、種明かしがされる終盤で、急激に物語のスケールは小さくなってしまう。
終盤で描かれる内容は、当事者にとって重要な物事であることを理解はできるが、それまで描かれた悲惨な世界とのギャップで感情移入が困難になっており、一部の人物だけで盛り上がってド派手にバトルをされても、筆者は全くノれなかったというのが正直なところだ。
本作のシナリオに隠された「種」は、日本のゲーム、漫画、アニメ等の創作において過去に幾度か挑戦が試みられたものの顰蹙を買ってしまった作劇展開と同じであり、本作もその失敗と同じ轍を踏んでしまったように思う。人によっては、魅力的だった序盤~中盤の物語まで色褪せしまったと感じてしまう可能性もあるだろう。
終盤の展開さえ良ければ、胸を張って傑作であると言えただけに、非常に残念である。
総評
ゲームシステム及び仕様の不備、シナリオ終盤の展開といった問題点はあるものの、ゲーム部分、特に戦闘はよく出来ており、今後のコマンドバトルにおける1つの理想的なモデルとして参考にされるべきものだと言える。
大手を振って神ゲーとまで称賛するのは難しいが、良作RPGの1つとして捉えるのは十二分に可能な作品である。
本作がGOTY級であるかどうかは、今後発売されるタイトルとの相対評価に委ねられるだろう。